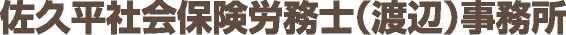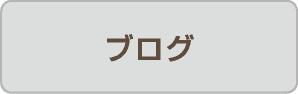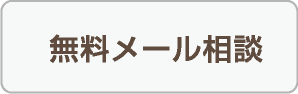2020年7月7日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑭
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
裁判所はどんな検討を経て判断を下したのかを見ていきます。
まず、原告、被告双方の主張を踏まえ、医師の診断書中、日常生活能力の判定の各項目及びその程度の記載の評価について次の情報を基に相当性を検証するとしています。
①病歴・就労状況等申立書の記述
②証人(原告の母)の供述
③証人(原告の中学校時代の担任)
次回に続く
2020年7月5日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑬
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
本件における裁判所の判断に至るまでの手法を大まかに言うと次の通りです。
1.判断の根拠は障害認定基準に求める
2.検証の材料は
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)おそらく原告の申し立てによるであろう証人の証言
これらの検証材料を丹念かつ詳細に検証し、その評価を明確にしています。
なお、(3)は裁定請求、審査請求、再審査請求では認められていないものです。
だからこそ、(1)(2)の一言一句が重いものであることがわかります。
次回に続く
2020年7月4日
「障害基礎年金不支給処分取消訴訟(知的障害)」⑫
◆平成30年の東京地裁判決を取り上げます。
ここで本訴訟の流れを時系列で見ると
H25.12.25 裁定請求
H26.3.3 不支給処分
H26.3.24 裁定請求
H26.7.23 棄却
H26.7.26 再審査請求
H27.3.31 棄却
H27.9.1 提訴
H30.3.14 判決
提訴後のH28.9.1に、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態調査の結果,精神障害及び知的障害の認定において,地域によりその傾向に違いがあることが確認されたことに伴い,専門家検討会による検討を経て,「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が施行されました。
原告側は、仮にこのガイドラインのルールを当てはめると,日常生活能力の程度及び日常生活能力の判定平均を前者が4,後者が約3.57で,障害等級1級又は2級に該当することになる旨を主張しました。
この主張は検討対象から外されましたが、今後不服申し立てをされる方々の事例の参考にはなるものと思われます。
次回に続く